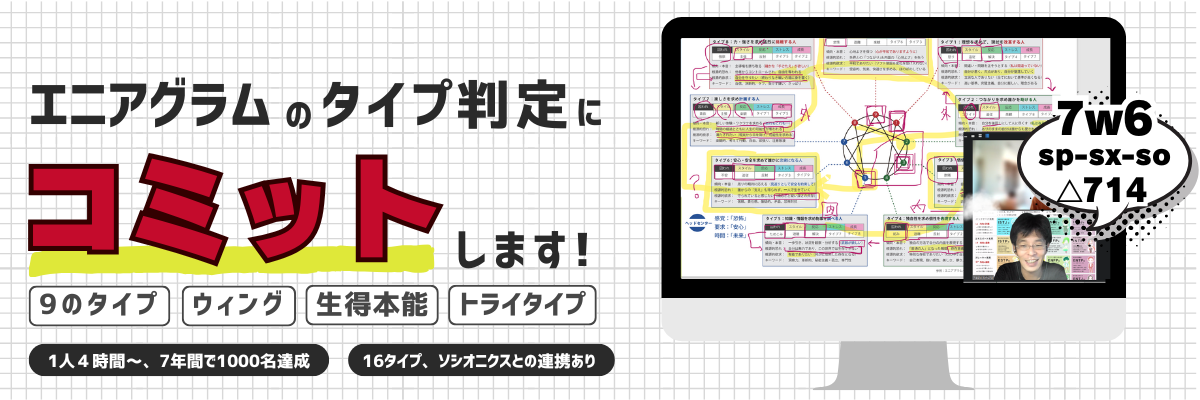【エニアグラム】タイプ6「忠実な人」の発達障害|「不安」の設計図とグレーゾーンの生きづらさ
「もし、最悪の事態が起きたらどうしよう…」 「これで本当に合っているだろうか…」
タイプ6:忠実な人は、「安全」と「安心」を強く求め、そのために「信頼できる仲間やルールに忠実であろう」とする動機(心のクセ)を持つ人たちです。 その慎重さや、万が一に備える準備力は、組織やチームにとって欠かせない「強み」です。
でも、もしあなたが「発達障害グレーゾーン」の特性(例えば、衝動性や、予測不能なことへの強い不安)も併せ持っていたとしたら…?
「最悪の事態を想定しすぎる」心と、「不安になると衝動的に動いてしまう」脳の特性が、自分の中で混乱を起こしてしまうかもしれません。 安全を求めれば求めるほど、不安で動けなくなってしまう…それが、タイプ6:忠実な人特有の「生きづらさ」のデザインパターンです。
この記事では、その生きづらさの「設計図」を一緒に読み解き、どうすればその「不安」と上手に付き合い、「信頼」という強みに変えていけるかを考えていきましょう。
ひよこ君とフクロウ君の「タイプ6」談義
ひよこ君: 「フクロウ君、どうしましょう…! メール1通送るのに、もう1時間も悩んでて…!『これで合ってますか?』って上司に5回も確認しちゃいました…」
フクロウ君: 「確認しすぎや(笑) ひよこ君はタイプ6:忠実な人の『不安』の設計図がフル稼働してるな。失敗を恐れるあまり、安心材料(=上司の確認)を無限に集めてまう癖や」
ひよこ君: 「だって、もし間違ってたら…って思うと怖くて…。でも、不安すぎてパニックになると、逆に『えいやっ!』って何も考えずに決断しちゃう時もあって…」
🦉 フクロウ君: 「それや! ADHD傾向の『衝動性』とタイプ6:忠実な人の『不安』がミスマッチを起こしてる典型例やな。『不安すぎてフリーズ』するか『不安すぎて暴走』するか…。今日はその『不安』という名のアクセルとブレーキを、ちゃんとコントロールするデザインを学ぼか」
タイプ6の「生きづらさ」の設計図
タイプ6:忠実な人の生きづらさは、「安全・安心を求める」という設計図が、発達障害の特性によって「過剰な不安」や「極端な依存」として現れる点にあります。
ADHD傾向 × タイプ6:忠実な人:「不安」と「衝動性」の矛盾したループ
もしあなたがADHD傾向の「衝動性」や「不注意さ」を持っている場合、「不安」と「行動」が矛盾した形で結びつきやすくなります。
- 不安による「フリーズ」と「暴走」 最悪のケースを想定しすぎて、不安で行動が「フリーズ(停止)」してしまいます。しかし、その不安が限界まで高まると、今度はADHD傾向の「衝動性」が発動し、「えいや!」と深く考えずに決断を下してしまいます。そして後から「あの判断は本当に正しかったのか…」と、さらに深い不安のループに陥ります。
- 無限の「確認行為」 「不注意さ」への自覚があるため、ミスを恐れる気持ちが人一倍強くなります。メールを送る前、資料を提出する前、「これで合っていますか?」と上司や同僚に何度も何度も確認します。しかし、タイプ6:忠実な人の設計図では、確認しても不安は消えません。むしろ「確認したけど、まだ見落としがあるかも…」と、さらに確認を重ねてしまいます。
- 過剰準備による時間切れ 「もしかしたら、〇〇が起きるかもしれない」という不安から、本来必要のないタスクや、ありえないシナリオへの対策まで過剰に準備してしまいます。その結果、本当に重要なタスクに使う時間がなくなり、締め切りに追われてパニックになる…という事態を招きます。
ASD傾向 × タイプ6:忠実な人:「ルールへの依存」と「変化への恐怖」
もしあなたがASD傾向の「こだわりの強さ」や「予測不能なことへの強い不安」を持っている場合、タイプ6:忠実な人の「安全を求める」設計図が、「ルールへの絶対的依存」という形で現れます。
- マニュアルがないと動けない マニュアルやルールは、タイプ6:忠実な人にとっての「安全地帯」です。ASD傾向が加わると、そこに書かれていないことは「やってはいけない未知の脅威」と解釈され、何もできなくなります。
- 予定変更への極度なパニック ASD傾向は「予測可能性」を求めます。タイプ6:忠実な人の「安定」への欲求と相まって、急な予定変更は「安全が脅かされた」というパニック反応を引き起こします。カレンダーにあった予定が一つ消えただけで、その日一日のすべてが崩れたように感じ、何も手につかなくなるのです。
- 暗黙のルールがわからない不安 ASD傾向ゆえに「こういう場面でどう振る舞うべきか」「これは言っていいことか」といった暗黙のルールが読めません。これがタイプ6:忠実な人の「間違いたくない」という不安を常に刺激し、人前でひどく緊張したり、失敗を恐れて行動を避けたりする原因になります。
ひよこ君とフクロウ君の「判断の恐怖」
ひよこ君: 「ぼく、自分で決めるのが怖いんです…。『どうすればいいですか?』って、常に誰かに指示を求めてしまいます…。間違えるのが怖くて…」
🦉 フクロウ君: 「それもタイプ6:忠実な人の『安全な権威に頼りたい』っていう設計図やな。自分で判断することは、間違える可能性(=危険)を自分で引き受けることやから、怖く感じるんや」
ひよこ君: 「そうなんです! でも、頼りにする人を間違えて、変なルールに従っちゃって失敗したこともあって…もう何を信じたらいいか…」
🦉 フクロウ君: 「わかるで。その『信頼できる何か』を探し求める旅こそが、タイプ6:忠実な人のテーマなんや。大丈夫、外側の『誰か』に頼る前に、内側の『自分』に小さな信頼を置くデザインをすればええんや」
タイプ6の「自分カスタマイズ」実践ガイド(支援とセルフケア)
あなたの「慎重さ」は、危険を予測する素晴らしい「強み」です。その強みを「不安による停止」ではなく、「安全を生み出す行動」に変える工夫(カスタマイズ)を見ていきましょう。
1. 「安全」をデザインする(最悪シナリオの言語化)
タイプ6:忠実な人に、抽象的に「大丈夫です」と言っても効果はありません。不安は「見える化」することで初めて制御可能になります。 「最悪の場合、こうなります。そして、その場合の対処法はこれです」と、**最悪のシナリオと、その対策を具体的に言語化(デザイン)**しましょう。 「もし〇〇が起きても、この手順で対処すればいい」とわかることが、タイプ6:忠実な人にとっての本当の「安心材料」になります。
2. 「確認」にルールを設ける
無限の確認行為を止めるには、「確認のための新しいルール」を作ります。 **「確認は2回まで」「質問は1日のうち、午前と午後の2回にまとめる」**といったルールを、上司や支援者と合意するのです。 これはタイプ6:忠実な人が従いやすい「ルール」です。そして、「2回確認したら、それで十分です。それ以上は不要です」と、信頼できる人(権威)が「保証」を与えることが、内的な不安を抑える助けになります。
3. 「小さな決断」の練習で、自律性を育てる
「自分で決める」という恐怖は、小さな成功体験を積むことで乗り越えられます。 まずは「昼食は何を食べるか」「どのペンを使うか」といった、**失敗してもリスクの低い「小さな決断」**を自分一人で決める練習をします。 そして、「自分で決めても、何も問題は起きなかった」という「安全の経験」を積むこと。これを少しずつ業務上の小さな判断へと広げていきます。(参照:ポジティブ行動支援 )
4. ASD傾向向け:環境を「構造化」し「予測可能」にする
ASD傾向が強い場合、環境の「曖昧さ」が不安の最大の原因です。 明確なルール、予測可能なスケジュール、役割分担をすべて文書化しましょう。「これがルールです」と目に見える形にすることで、安心感が生まれます。 予定を変更する場合は、「できるだけ早く」「理由と共に」予告します。「来週、〇〇の変更があるかもしれません」と事前に伝えるだけで、心の準備ができ、パニックを防げます。
5. 「不安と共に動く」練習(マインドフルネス)
不安を「ゼロ」にしようとするから苦しくなります。不安は「危険を知らせるアラーム」として役立つ、正常な反応です。 大切なのは、不安を消すことではなく、**「不安を感じたままでも、行動はできる」**と知ることです。 マインドフルネス(今ここにある感覚に意識を向ける瞑想など)の技法を使い、「今、自分は不安を感じているな」と、その感情を「観察」する練習をします。不安と自分を同一視せず、距離を置くスキル(メタ認知)を育てることで、不安に飲み込まれずに済みます。
6.「信頼関係」という土台を築く
タイプ6:忠実な人は「裏切られること」を何より恐れています。支援者は、**「一貫した対応」**を見せ続けることが全ての土台となります。 約束は守る。変更は事前に伝える。小さなことでも誠実に対応する。「この人は信頼できる」という安心感が一度築かれれば、タイプ6:忠実な人は最も忠実で、頼りになる協力者になります。
まとめ:「慎重さ」は、リスクを管理する「強み」
タイプ6:忠実な人のあなたが持つ「慎重さ」や「注意深さ」、「何が問題になるか」を予測する能力は、リスク管理、品質管理、コンプライアンス(法令遵守)、総務・事務など、「正確さ」と「堅実さ」が求められる仕事で、かけがえのない「強み」として輝きます。
あなたの生きづらさは、「心配性」という欠陥ではありません。 それは、あなたの「安全を守る」ための素晴らしい設計図が、「曖昧な環境」や「予測不能な変化」とミスマッチを起こし、過剰にアラームを鳴らしている状態です。
不安を「見える化」し、対策をデザインすること。 曖昧なものを「ルール化」し、予測可能にすること。 そして、「不安があっても行動できた」という小さな成功体験を、信頼できる仲間と共に積んでいくこと。
そうすれば、あなたの「不安」は、あなたとあなたのチームを危険から守る、最高の「リスク管理システム」になるのです。
(CTA共通パーツ)
一人で悩んでいませんか? あなたが感じている「生きづらさ」は、あなたの「性格(心の動機)」と「発達特性(脳のクセ)」が複雑に絡み合った結果かもしれません。 でも、その設計図を正しく読み解けば、それは「弱み」ではなく、あなただけの「強み」として活かす道が必ず見つかります。
「自分はダメなんだ」と責めてしまう前に。 まずは、あなたのユニークな「心の設計図」を知ることから始めてみませんか?
私たちは、エニアグラムと発達障害の専門知識(コーチング心理学)を活かし、あなたが自分を理解し、自分らしく輝くための一歩をデザインするお手伝いをしています。
→ まずは自分のタイプを知る(無料診断やお試しセッションへ) → もっと詳しく知りたい(個別相談サービスへ)
本記事は、一般社団法人コーチング心理学協会の提供する「発達障害支援コーチング」の理論と資料を参考に、著者の知見を加えて執筆されました。 引用元: 一般社団法人コーチング心理学協会 ( https://www.coaching-psych.com/event/ddsc/ )
自分のタイプを決めたい
自分のタイプを決めたい
4時間で、自分のすべてがわかる!
行動のクセ、人間関係のパターン、なぜ動けないのか。その答えは、エニアグラムのタイプでわかります。
このセッションでは、エニアグラムの5つの視点
──「9の性格タイプ・ウイング・生得本能・フロイトモデル・健全度」をひとつに統合。
海外のエニアグラムの理論を通じて根源から紐解いていきます。
無料講座
お客様限定|タイプ論の月例会
タイポロジースクール
エニアグラム生得本能の会
2025.11.19
水
21:00
23:00
リソ×ラスのエニアグラム実践編を通じて、健全度が通常になったとき、どの生得本能が現れるかを見ていきます。 健全なときは、3つの生得本能をバランスよく使えますが、健全度が落ちると優位と盲点がハッキリとでます。 その状態を可視化していきましょう!
対象
エニアグラムオンライン【コミット】参加者様
上記のお客様の紹介者様
形式
グループ講座
日時
2025年11月19日(水)21~23時
場所
Zoom
料金
無料
定員
5〜8名
備考
開始60分前にご参加いただければ、個別でフォローアップを致します。
当日の流れ
20:00 受付
フォローアップセッション。エニアグラム×16性格診断のご質問にお答えします。
21:00 1部の開始
自己紹介や本日のテーマや理論の紹介を行います。
21:30 グループワーク
数人のグループに分けて学んだ内容の共有や意見交換を行います(人数によってはやらない場合もございます)
22:00 2部の開始
1部の内容を反映して、二部の内容について共有します。
22:20 グループワーク
30分ほどグループワークを行います。23:00にいったん終了します
23:00 Q&Aの会
ご希望のお客様に限り残り、エニアグラムオンラインの質問についてお答えします。
講座案内
9つの性格タイプ一覧
サブタイプ一覧
木村真基
Kimura Naoki
ウェブデザイナー/エニアグラム講師
プロフィール
「ひよこ君とフクロウ君のエニアグラム( 9つの性格 )講座」の運営者。本業はホームページ制作。ホームページの効果を実証するために、ひよこ君とフクロウ君のエニアグラム講座を開始。気づけば、エニアグラム、16性格診断、ソシオニクスのタイプ判定を生業にしている。
・エニアグラム:3w4sp-sx-so&Tritype386
・16の性格:ENTP(討論者)&ILE(ENTp)(発明家)
・ストレングスファインダー:着想、戦略性、学習欲、達成欲、自我
などの性格類型を活用して、自分らしく生きる方法を提唱中。